臨床仏教なるものに触れる
2017年10月10日(火)
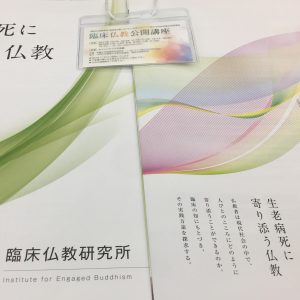
全10回の臨床仏教公開講座の第1回に出席しました。
京都駅近くのキャンパスプラザ京都が会場でした。
冒頭に御挨拶があり三人の講師による記念講演がありました。
お一人目は第2回で講師を担当されるカール・ベッカーさん。
「祖父を介護する様子を子どもに見せないと、子どもは自分の親を介護してくれると思うな!」
機会があればいろいろな方にもお伝えしていきたい言葉が印象に残りました。
お二人目は今回の記念講演だけのご縁だったチャプレンの窪寺俊之さん。
「『きく』ことの意味には『聞く』『聴く』『訊く』『利く』『効く』がある」
スピリチュアル・ケアでのきき方の違いがこれほど多様にあるというのは学びでした。
お三人目は第10回で講師を担当される神仁さん。
「台湾ではトレーニングを経た僧呂が臨床仏教宗教師として国立病院などで活躍している」
聞いたことはありましたが写真を添えて具体的に紹介していただけたのは有り難かったです。
実は冒頭の花園大学総長の河野太通老大師のお言葉が最もハッとさせられました。
「人間は自分が最も大切にしているところに執着する。自己が信奉する神や仏すらも離れねばならぬ。」
臨済宗ならではの意味合いも含まれていると思いますが臨床仏教というものに欠かせぬものだと思いました。
自分が正しいと思ったり大切に思っているものは、あくまで自分にとってのことでしかありません。
他人が正しいと思ったり大切に思っているものは、自分とは全く違うことだって多々あるでしょう。
「他者に寄り添うときには無力な自分でいなければ本当には何もできない」というのは今日の一番の学びでした。